| 第一部 基調講演「日本の電子機器生産動向と省エネの重要性」 IHS iSuppli アイサプライ・ジャパン株式会社 副社長・主席アナリスト/ジャパンリサーチ 南川 明 氏 |
| ■概 要
世界の電子機器動向は今後10年でインフラ、医療、車載、スマートフォン、省エネ家電などを中心に大きな変化が見込まれる。一方、円高の影響もあり日系電子機器生産は伸び悩んでいるが、新しい動きも出始めている。日本のお家芸ともいえるエコ技術は日本の電子機器メーカーにとってさらに重要な技術となってきた。ここでは2020年までの世界の電子機器動向と日本の電子機器メーカーのポジション予測を行ってみる。 |
| 第二部 企業講演「最も効率的・最適なストレージ・ソリューションとは?」 サムスン電子株式会社 日本総括(DS)部長 金 相局 氏 |
| ■概 要 今日のIT業界においてビッグデータの出現が、ソフトウェア・ハードウェアの双方を変化させる大きな引き金となりました。そのような中メモリーの消費電力は、データセンター全体の消費電力において大きなウエイトを占めています。サムスンはユーザー企業の皆さまに、超低消費電力のメモリーを提供することで、データセンターTCOを削減し環境にも優しいストレージ・ソリューションを提案しています。 |
 |
第一部 基調講演 「日本の電子機器生産動向と省エネの重要性」 IHS iSuppli アイサプライ・ジャパン株式会社 副社長・主席アナリスト/ジャパンリサーチ 南川 明 氏 |
| アジアを中心に拡大する中間層 |
| 世界の全人口である70億人のうち、1日2米ドル(年間730米ドル)以下で生活する貧困層が約40億人います。モノがあふれた日本にいると忘れがちですが、全世界の大半は日本人とは比較にならないほど貧しい生活水準の中で生きています。その一方で、貧困層を抱えるBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の経済規模は、2040年には現在の経済大国トップ6であるアメリカ、日本、ドイツ、フランス、イギリス、イタリアの合計を上回ると予測されています。貧困層を抱える国々の台頭は、世界経済の構造も政治的なパワーバランスも大きく塗り替えるでしょう。 これら新興国における個人消費の拡大は、世帯可処分所得が5000~3万5000米ドルである中間層の拡大がけん引しています。特にアジア新興国における中間層は、2000年に2億2000万人から、2010年には9億4000万人に拡大しました(図1)。この値は米国、欧州連合(EU)を合わせた人口規模を上回ります。今後に向けては、2020年にはアジア新興国における中間層が20億人に拡大すると見込まれています。世帯可処分所得が3万5000米ドル以上の富裕層2億3000万人と合わせると、アジア新興国全体の人口の2/3が、エレクトロニクス消費が可能な中間層以上になると予測されます。 この予測通りに行けば、2010年から2020年までにアジア新興国で約10億6000万人のエレクトロニクス購買層が誕生します。やはり、この10年間はアジア新興国地域をターゲットにした戦略が求められます。また、その他の新興国で誕生するエレクトロニクス購買層は約1億8000万人で、これを加えると全世界で12億4000万人のエレクトロニクス購買層が誕生することになります。その他の新興国の中では、ブラジルとパキスタンが市場規模と成長率から注目されます。 まさに大量消費・大量生産の時代の真っただ中に位置しているのです。 |
図1 新興国の中間層が急拡大中 |
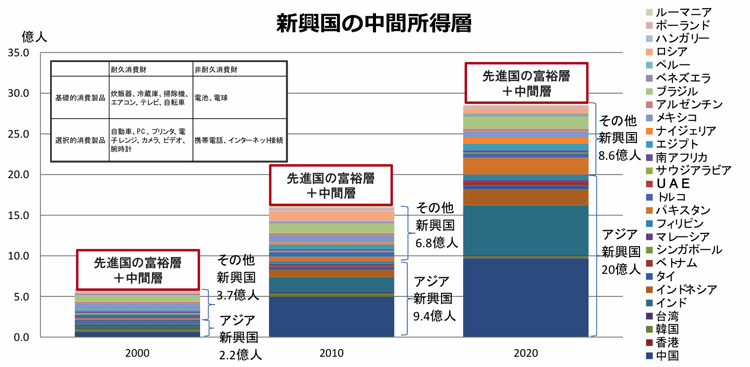 |
| 電力の需給バランスが崩れる可能性 |
| 世界の電力需給バランスを見ると、今後アジアでの消費が急増していることがわかります。アジアでの中間所得層急増が背景にあります。今後10年で急増する消費をまかなうためには今まで以上の供給能力拡大を行う必要があり、原子力問題の起きている現在では需要を抑え込む方が現実的であると思われます。電力料金値上げも考えられますが、電子機器単体でのエコ技術導入が最も注目されることになるでしょう。たとえばインバーターが注目されることになります。世界の電力消費の約55%はモーターを駆動するために使われています。そのうちの、約2割にしか、インバーターは使われていません。日本は100%インバーターエアコンですが、アメリカはまだ2割ぐらいです。中国はまだ2割にも達していないですね。ただ、オン、オフだけのエアコンです。当然、インバーター化することによって、エネルギーの削減効果というのは30%から40%あります。
一般的な製造業の工場の電力構成ですが、約6割はモーターを駆動するために使われています。やはりこの2割にしかインバーターは使われていません。当然、インバーターが使われれば、エネルギーの削減になるわけで、仮に日本の例を考えると、日本の場合は約6割の電力をモーター駆動に使っています。日本ではその3割にインバーターが既に使われています。7割には使われていないということです。もし、その7割にインバーターを今つけたとしたら、現実的にはちょっと古いものにはつけられないのですが、インバーター化で30%の効率化を図れるとしたら、理論的には、全電力の12%をすぐに削減することが可能です。 |
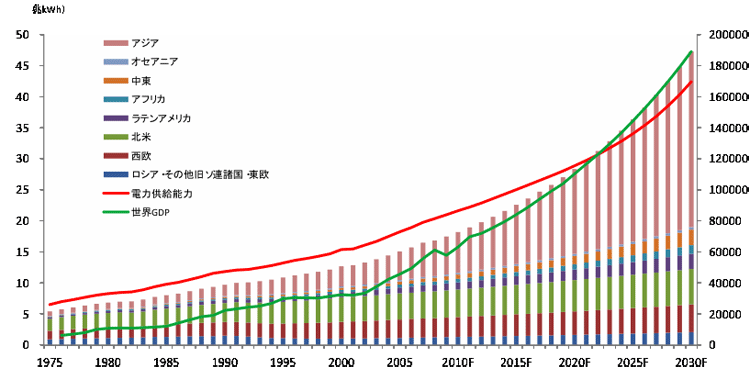 |
| 電子機器は今後10年で急拡大する |
| 世界の電子機器生産金額(ハードウエアのみ)は2000年の1兆2200億ドル(約130兆円)から2010年に1兆6600億ドル(170兆円)へ拡大し、2020年には2兆7500億ドル(270兆円)へと大幅な拡大が期待されています。過去10年の間に起ったITバブル崩壊とリーマンショックによりインフラ投資抑制、消費低迷が電子機器の成長鈍化を引き起こした。今後10年間で経済停滞が1度はあると仮定しても、電子機器需要は大きな伸びを達成すると予測しています。背景には産業機器分野の成長と新興国の中間所得者層の拡大がある。過去10年で拡大した中間所得層が基礎的なエレクトロニクス機器(炊飯器、冷蔵庫、エアコン、テレビ、携帯電話など)を購入しました。しかし、2001年と08年の2度の経済停滞によりインフラ投資抑制と先進国消費低迷により電子機器市場規模は伸びが低くなっていました。しかし、今後はさらに増加する消費人口とインフラ投資(特にオートメーション、BEMS/HEMS、エネルギー関連機器、医療)への各国の取り組みが期待されています。 |
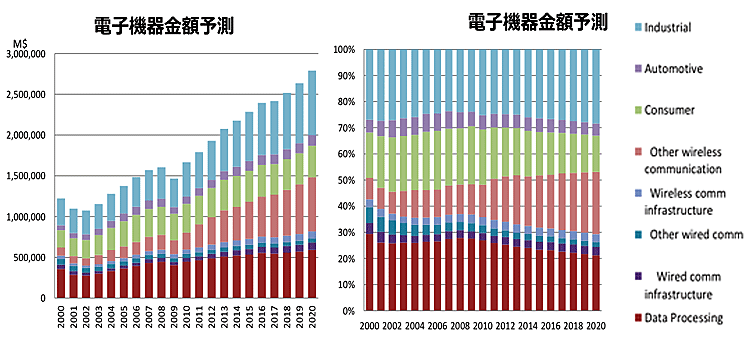 |
| スマートフォンとタブレットは2020年までさらに拡大が見込まれています。タブレットはノートPCとの境界がなくなって仕事に使われるようになると見ており、スマートフォンは他の電子機器の市場を少しずつ浸食することで拡大を続けると予測しています。現状ではコンパクトデジカメ、パーソナルナビゲーション、ネットブックPC需要を侵食しており、今後はムービー、TV、パーソナルDVD、ゲーム需要を取り込み、さらにパーソナル医療と繋がったり、お財布機能の強化、コンシェルジェサービスなどの機能追加により継続成長が期待されます。 産業分野で注目されるのはエネルギー関連機器、特に再生可能エネルギー、スマートグリッド、HEMS/BEMS、オートメーション分野です。この分野で重要な事は各国の政策で推進されるエネルギーインフラ、医療の改革に伴う変化です。 スマートグリッドは各国で導入が急がれています。太陽光発電や風力発電は自然エネルギーであるため、時間帯や気候条件の変化によって電力量が大きく変化します。現在の電力網では2割以上の新エネルギーを導入すると、逆潮流や電源が不安定になるなどの問題を抱えているため、スマートグリッドの導入を急いでいるのです。既に欧米や中国でのスマートグリッド導入計画が着々と進められており、2020年頃には半導体の牽引役として注目されているはずです。医療は各国で問題になっている健康保険破たんが背景にあります。米国では国民健康保険が存在しないため医療費が高額で払えなくなる人が続出、個人破産の1/4が医療費負担に耐えられないことが原因となっています。欧州では、やはり健康保険の財源不足で医療費が引き上げられたり、経営不振で閉鎖される病院が増加しています。特に先進国では高齢化が進み、医師不足、病院不足が目前の問題になっています。これを解決するために家庭での医療に比重を移すことが考えられています。家庭での健康管理、病気の予防、検診を充実させ、病院では専門家による治療に専念する分業体制を整えることで医療機関の有効利用を促すことになります。 |
| page top↑ |
 |
第二部 企業講演 「最も効率的・最適なストレージ・ソリューションとは?」 サムスン電子株式会社 日本総括(DS)部長 金 相局 氏 |
| データ爆発がデータセンターの負担に |
| スマートグリッドには重要な部分がいろいろありますが、私の見立てではデータセンター(DC)も重要ではないかと思っています。サーバーは、平均して大体40ギガ(ギガは10億)バイトから50ギガバイトのメモリーが使われます。サーバー全体の約20%の消費電力を占めています。20%といえば大きなものなので、スマートグリッドやIT産業にメリットを与える役割もなかなか大きいです。そのために我々サムスン電子も努力して参ります。 この10年間で、電子機器は10倍ほどに増えています。2013-14年には100億台まで増えるものと見られています。5-6年前は、スマートフォンはまだそれほど普及していませんでしたが、最近はスマートフォンやタブレット端末が増え、すべての機器がインターネットにつながっています。人間の頭脳では処理できないほどデータ量が増えています。実際に発生しているデータ量は3年ほどで3倍に増えています。 それに基づくDCでの課題が三つあります。まず1つ目が工程費用を減らすことです。いろいろなハードウエアを設置するには費用が必要です。いま存在するハードをどう効率的に使用するか。スペースに関してでは、いま100台を設置している分と同じスペースに200台を設置できないかといった効率化に関することです。 2つ目は、大きな負担になる電気料を含めて、トータルコストを下げることです。低消費電力をどのようにして実現するかということです。 3つ目は、停止したDCを早めに復旧することです。DCが停止すると復旧するまでの時間が利用者には多大な影響を与え、サービスを受けられないという大きな問題が発生します。 |
| 負担をどう取り除くか | |
| 以下、順番に説明します。 1つ目のIT効率化ですが、仮想化が05-06年ごろから始まりました。仮想化に問題がないかですが、1台あたりいろいろな動作を要求されるため、サーバーに負担がかかります。ただ、中身を見ると中央演算処理装置(CPU)の性能は問題ありません。問題になるのは、データを保存するストレージ(外部記憶装置)の性能がやや低いことです。データの保存先はハードディスク駆動装置(HDD)かソリッドステートドライブ(SSD)に分かれますが、性能を評価して比べると、SSDのほうが速く、約14倍の差があります。ただ、価格が高いのが難点です。ですが、価格と性能を合わせた二つの変数で比較すると、SSDの方が大幅に優れています。 |
|
| 2つ目について説明します。世界の年間の電力消費量は1万8118テラ(テラは1兆)ワットほどで、うち1.5%の272テラワットをDCで消費します。国家で比較すると、イタリアをやや下回るほどの数字です。これは決して少なくない数値であり、これをいかに減らすかが重要です。 サムスンが何をするかについて説明します。弊社にも回路線幅50ナノ(ナノは10億分の1)メートル台や20ナノメートル台のDRAMがありますが、強みは先端技術で新しいものを早く市場に投入できることです。台湾系の会社などでは、まだ40ナノメートルや50ナノメートル台が主な製品になります。弊社ではことし20ナノメートル台に本格的に進みます。50ナノメートル台と比べると、電力消費量をシステム上で29%ほど減らすことができます。 大きな問題は熱です。50ナノメートル台は61.9度まで上昇します。20ナノメートル台は、実際のメモリーの表面上で目指した温度で、40.8度。ほぼ28度の差があります。冷却システムでも簡単にコストが下がることがわかります。 3つ目です。DC管理における三つの課題が、システムが停止している時間、目標復旧時間、そして信頼性です。サービス品質保証(SLA)に基づいて考えなければならないのが、サーバーが何回停止するかということであり、停止から何秒、何分かかって復旧できるかが、DC管理者にとっては一番重要であると考えています。 弊社の製品がどんなメリットを持っているかについて説明します。例えばサーバーのストレージであるSSDには銀行や病院、個人情報など本当に重要なデータが保存されるところです。設計、工程などの一番いいものを選択して、先端チップを使って組み立てるのがサムスンのSSDです。エンジニアも数百人おり、組み立ても評価も自社工場で実施しています。全てのソリューションを持っているのがサムスンの強みです。 お客さまよりサムスンの製品が評価された実際の事例をご紹介します。米マイクロソフト(MS)のテクノロジーセンターは、我々の製品である50ナノメートルのDDR3とHDDの組み合わせと、グリーンメモリーの20ナノメートルDDR3とSSDの組み合わせを比べ、目標復旧時間を2.6倍速くできることを確認しました。メモリーとストレージだけで比べると、59%消費電力を削減できました。米デルのソリューションセンターでは、HDDと比べて23倍速かったです。 |
| サムスンの提案 |
 |
本日の発表のキーワードです。50ナノメートル台のDRAMとHDDの組み合わせと、20ナノメートル台のDRAMとSSDの組み合わせの差は、トータルで見ると1ナノメートルあたり9万ドルほど節約できます。 いままでグリーンメモリーの実証を継続して行ってきました。これまで第一、第二段階が終わり、ことしは第三段階です。第3段階で弊社が生産供給できるのが、20ナノメートル台DDRとSSDです。DDR4は恐らく14年に始まるので、DDR3、同じく1.35のDDR3で、8ギガビットも考えています。そのままさらに消費電力が下がる製品を作り、供給できるよう努力して参りたいと思っています。 結論ですが、スマートグリッドで一番重要であるDCにおける大きな課題や要求事項は、性能、消費電力、信頼性です。その三つについて、サムスンは20ナノメートル台DRAMである、DDR3とSSDの組み合わせを提案していきたいというのが、本日の結論です。それを提供することでサーバー内の熱が下がり、地球環境にも役に立つソリューションであると思っています。 世界にあるサーバーの総数は3200万台ほどです。理想の話ですが、40ナノメートル台とHDDの組み合わせを、20ナノメートル台とSSDの組み合わせに替えると、年間40テラワットの電力を節約できます。その分を発電するには、二酸化炭素(CO2)が2800万トン発生します。それを無くすためには7億1000万本の樹齢10年以上の木を植える投資が必要です。消費電力が低いものはDCにもメリットがあり、エネルギーも節約できるので、地球環境を守ることができます。 |
| page top↑ |
|
|||||
Copyright 2012 THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN,LTD.

